(INTERVIEW)
【INTERVIEW】人工子宮が当たり前になったら?──「PARALLEL TUMMY CLINIC」が問いかける “もしも” の世界 〜後編〜

前編では、没入型インスタレーション「PARALLEL TUMMY CLINIC」の企画背景や、人工子宮をめぐる未来の世界観について伺いました。後編では、映像作品の制作エピソードや、長谷川愛さんと山田由梨さんのやりとりから生まれた本作の“没入感”のひみつに迫ります。
インタビュアー: 黒田 純平(株式会社マガザン)
インタビュイー: 長谷川 愛(アーティスト)・ 山田 由梨(作家・演出家)
ライティング: 小倉 ちあき
前編に引き続き、ここからは、本展についてさらに掘り下げていきます。まず、山田由梨さんが今回の企画に参加することになった経緯を教えてください。
山田由梨さん(以降、山田):SHUTLの企画運営側からお声がけいただいたのは、2023年の初め頃でした。
「人工子宮」というテーマは、私にとってそれまで扱ったことのないモチーフではありましたが、最初に聞いたときから、これは挑戦しがいのある題材だと感じました。
愛さんが考えた制度設計や未来の社会背景をどう物語として立ち上げていくか、自分のこれまでの活動──演劇や脚本を通じて社会構造に光を当ててきた経験が、きっと活かせるのではないかと思ったんです。
「人工子宮」は、愛さんが長年かけてリサーチしてきたテーマです。
その蓄積された知識や思考をベースに、「人工子宮のある50年後の世界で生きている人々の日常や感情を、会話劇として描く映像作品をつくる」という役割を今回担うことになりました。
私がこの作品で大切にしたのは、“50年後の世界で、誰もが一度は人工子宮を使えるようになっている”という設定に、観る人が自然と入っていけるようにすることでした。その設定自体がいろいろなものを飲み込まないと本当は入り込めない設定でもあって、まず疑問が生まれてくるはず。たとえば、制度の仕組みや使用資格の取得方法、あるいは中絶がどう捉えられているのか、同性愛者の権利がこの未来社会でどう位置づけられているのか、など──入れたい情報は本当にたくさんありました。
でも、あまりに情報を詰め込みすぎると、“ただの説明”の動画になってしまう。
そうなってしまうと、登場人物の感情や、彼らの人生に共感したり想像したりする余白が奪われてしまうんです。
それをすっと飲み込んで、観る人が入り込めるように、今回はとにかく「情報の配置」に一番気を配りました。溢れんばかりの情報と思考がそこにあるものを、いかに削ぎ落として、ちゃんと登場人物の感情を想像できるように作品・脚本に落とし込んでいくか。それが自分にとっての一番の役割だったと感じています。

山田由梨
長谷川愛さん(以降、長谷川):最初に「一緒にやりたい」と思ったのは、まさにその点です。私は制度や科学技術の未来像を組み立てるのが得意だけど、それを「人の言葉」に変えるのが難しい。山田さんがそこを担ってくれたことで、世界観が一気に血の通ったものになりました。
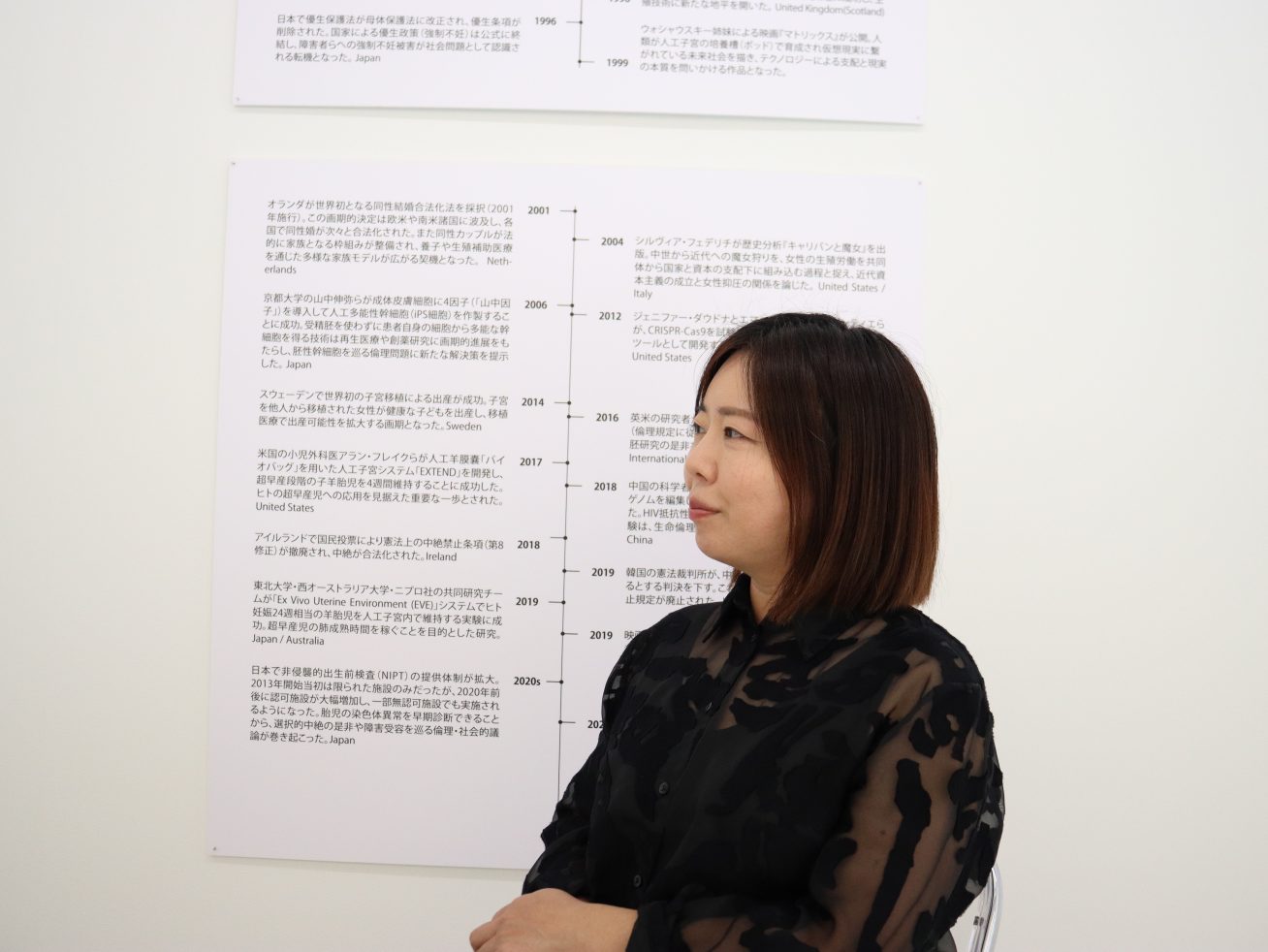
長谷川愛
コラボ作品を制作する上で、作品の構想を話し合ったりリサーチを行ったりしながら、初期の段階でLARP(ライブアクションロールプレイング)セッションを一緒にやりましたね。LARPのアーカイブ映像も本展では重要な要素だと思いますが、その時のことなどを教えてください。
山田:私は演劇をやっていることもあって、即興演劇は比較的身近なものでした。
設定を与えられて、その役になりきって即興で喋るということはこれまでも経験があったので、今回もむしろスッとその場に入り込めた感覚がありました。今までは、机上で議論したり、情報として言葉にして話し合ったりしていたことが、実際に演じてみることで身体を通して立ち上がってくるような感覚があって。 「実際、自分はこの状況でどう感じるんだろう?」とか、「このセリフって本当に言えるのかな?」という葛藤や違和感が、肉体を通じて見えてくるんですよね。 それが、愛さんがこれまで積み重ねてきた思考に、自分が身体レベルで近づいていくきっかけになったように思います。
印象に残っているのは、参加いただいた武田さんが演じた“10歳の男の子”の役です。子どもの視点から世界を見ていくことで、すごくフラットに物事を捉えることができたし、ある部分では「これはいいかもしれない」と感じながらも、同時に「もしかしたら別の問題を生むかもしれない」という想像までできるような設定だったのが、とても面白かったですね。それから、愛さんが“保守的な母親”の役を演じようとしたときのことも印象深いです。 ご本人は「悪役やります!」と宣言していたのに、やっぱりリベラルな価値観が滲み出ちゃうんですよね(笑)。
設定としては保守的なはずなのに、どうしても愛さんらしさが現れてしまう。
そのギャップがすごく面白くて、「滲み出ちゃうよな〜」と、演劇ならではのリアルさを感じる瞬間でした。

LARPセッションの様子
鑑賞者の反応で印象に残っているものはどんなことがありますか?
黒田:このLARPセッションの映像も皆様しっかりと見てくださいますよね。
山田:その場で私たちがロールプレイして、発言を調整して試行錯誤しながら作っていった過程が、映像にもそのまま記録されていて、演劇的なライブ感をもっていたことも大きかったと思います。決められたことを演じるのではなく、制作中のプロセスそのものが創造的だったからこそ、観た人も面白く感じるんじゃないかと思います。
長谷川:展示形式を一人ずつの体験型にしたことで、より深く自分と向き合える時間になったという声も多く、それはいい判断だったなと思います。
そんなLARPセッションや打ち合わせも重ねて制作した映像「From the Parallel Tummy」の制作過程ではどのような印象が残りましたか?
長谷川:私、普段はあまり「役を演じる」という感じで映像を撮ることがないんです。セリフもそこまでしっかり覚えてもらうことは少なくて、どちらかというと、何回か“適当に”やってもらって、後から編集で良いところを選ぶっていうやり方が多いんですよね。でも今回は、セリフをきちんと覚えてもらって、ある程度一続きで演技してもらう形式だったので、この撮影は意外と難しいと思って、かなり緊張感がありました。それに、実際に演技が入ると「こういう風に演技指導するんだ」とか、「撮影の時点でここまで決めるんだ」みたいな発見があって、すごく面白かったです。
山田:私からすると、あの現場は“いつもの自分の現場”っていう感じでしたね。俳優が動くためには、感情だけじゃなくて“必要な情報”や“必要な言葉”があるんですよ。そこをちゃんと整えるのが、自分の演出の仕事だと思っています。今回は、愛さんが映像の質感とか、水のフィルターの感じとか、ビジュアル面の演出を考えてくれて、私は俳優の動きや感情面の演出を担当するという、自然な役割分担になっていた気がします。それぞれが、これまで培ってきた領域を持ち寄ってやれたのが、すごく良かったなと思っています
黒田:自分も美大時代に友人の映像作品に出演するという経験はあったのですが、改めて今回の撮影では皆様のプロフェッショナルを感じました。俳優さんたちも真剣に取り組んでいただき、緊張感のある撮影現場でした。特に最後、俳優さんがアドリブを加えてくれたときは個人的に鳥肌ものでした。

「From the Parallel Tummy」展示風景 撮影:山根香
最後の質問となりますが、生殖にまつわる価値観は今後も時代とともに変化していくと思います。今回の作品を、改めてどのように捉えていますか?
長谷川:今回この作品をつくる中で、個人的にもとても勉強になったと感じたのは、シルヴィア・フェデリーチの『キャリバンと魔女』という本を読んだことでした。その中で改めて気づかされたのは、「最近のディストピアって、突き詰めると半分くらいは資本主義の話だったんじゃないか?」という視点です。この本は資本主義が「魔女狩り」を通じ、女性から避妊や堕胎の技術を取り上げ、労働力となる子供を産み育てる機械として閉じ込め搾取してたのでは、と論じています。
たとえばマーガレット・アトウッドの『侍女の物語』のように、女性が“産む機械”にされ権力により支配される構造──そこでは女性からすべての権利が奪われて、生殖と労働力を搾取される。そうした地獄のような状況は、ある意味で私たちがすでに知っている“最悪”のかたちです。ただ、それがフィクションの中の話ではなくて「このまま女達の我儘で少子化が進んで労働力が減少してしまうのなら、それを現実にしても仕方ない」と言い出しそうな政治家たちが今、本当に存在している。この創作を通して、そうした社会構造の背後にあるもの──つまり資本主義が、性や身体、生殖といった領域にまで深く入り込み、私たちから様々なものを奪ってきたのではないかという問いに辿り着いたんです。ずっと誰かが、資本主義を批判していたけど古典的すぎて、もはやその問いを問う事が陳腐化している。
最近は、技術哲学の分野にも興味を持っていて、たとえばテクノロジーというのは自然や生命を“資源”とみなし、効率よく搾取・収集するための手段であるという考え方があるんですが、それってまさに資本主義がしてきたことと同じだなと。私たちはいま、資本主義を“批判すること自体”が難しくなっている社会に生きていると思います。批判しようとすると、「じゃあどうやって生きていくの?」とか、「現実的じゃないよね」と一蹴されてしまう。資本主義が一種の宗教のようになっていて、その“教義”から外れることが、ダサいとか、非現実的だとされる風潮がある。そんな中でこの作品を通して、“批判する自由”すら奪われつつある私たちの現状を捉え直したいと思いました。
山田:私も今回、愛さんが「人工子宮を“希望の技術”として提示したい」と話していたことが、本企画の大きな柱だったと思っていて、私自身もそこを目指して脚本を書いていきました。
長谷川:今って、もうすでに“ディストピア”じゃないですか。ディストピアの世界を生きているからこそ、それを描くのはむしろ簡単なんですよ。
山田:だからこそ今回は、あえてそれを“希望”として書く挑戦だった。そこが一番難しかったし、同時に重要だった部分でもあります。私が脚本を書くにあたって愛さんに最初に投げかけたのは、「人工子宮がもし支配的な男性や資本主義の構造に組み込まれたら、どう悪用されてしまうだろう?」という懸念でした。でも今回は、その視点を一旦脇に置いて、「もし、そうした支配から自由なかたちで人工子宮が存在するとしたら、それはどんな風に“希望”として機能しうるのか?」ということを考えていったんです。
この希望は誰の、どういう立場の人にとっての希望なのか──そこがすごく重要だと思っています。今回の作品には、中絶経験のある女性や、子どもを望みながらも持てなかった女性、あるいは同性カップルなど、多様な背景をもつ登場人物が出てきます。この人たちにとっての希望を描いているということは、50年後の未来の話であるけれど、むしろ“今この社会において必要とされている”という証でもあるんですよね。どうしてそれが必要とされているか、ひっくり返してそっちを考えなきゃいけないということに光をあてるプロセスだったと思っています。
長谷川:実際、日本では10人に1人の女性が中絶を経験しているというデータがあります。けれど、そうした事実がほとんど語られていないのは、それを“言えない”環境にあるからだと思うんです。だからこそ、希望の裏側には“言葉にできない痛み”があって、その裏返しの部分を見つめなければならない。
山田:愛さんが「人工子宮は“一瞬の痛み止め”かもしれない」と仰っていたのですが、痛み止めになりながら、希望になりながらも、テクノロジーが登場することで人をさらに悩ませてしまう側面もある。たとえば卵子凍結もそう。選択肢が増えたことで、悩む期間が延びたり、悩む幅が増えたりする。“可能性が広がること”が必ずしも幸せに結びつくとは限らない──そんな現実がある。だからこそ、こうした技術に私たちがどう向き合い、どう倫理を築いていくかが、これから試されていくんだと思います。
最後に、この展示を通して伝えたい、お二人の想いを聞かせてください。
長谷川:今までの女性達ーフェミニストだったり優生思想主義者だったり、様々な女達ーが、自由を求めて人工子宮を夢見てきたという歴史がある。私はそれにすごい勇気づけられて、作品を作らなきゃ!という想いに駆られていましたし、今回それを由梨さんが受け継いでくれた。フランス革命以後の"人権”って結局男性のものでしかないように感じられるし、いまだに日本も状況は良くならないし、またバックラッシュが強まっている状況だから50年後も由梨さんも私も戦ってるかもしれない。そんな感じで、これからも戦う人達があらたに登場し続けるんだろうなと考えながら作っていました。
これは答えを示す展示ではありません。むしろ、問いを手渡す展示です。テクノロジーの進化を、希望にも脅威にもできるのは、今の私たち自身の想像力です。人工子宮が当たり前になった未来を描くことで、今をどう生きるかを見直すきっかけになればと思っています。
山田:未来は誰かが作るものではなく、私たち全員が関わっていくものです。この展示が、その入口になれば嬉しい。物語や映像を通して、自分の立場や感情を見つめ直す時間をつくれたら、それだけで大きな意味があると思っています。
(PROFILE)
長谷川愛 / Ai Hasegawa
アーティスト。バイオアートやスペキュラティヴ・デザイン等の手法によって、生物学的課題や科学技術の進歩をモチーフに、現代社会に潜む諸問題を掘り出す作品を発表している。 IAMAS、RCA、MIT Media Lab卒。2023年度から慶應義塾大学理工学部准教授。MoMA、森美術館、上海当代艺术馆、国立女性美術館(NMWA)、アルスエレクトロニカなど、国内外で多数展示。著書に「20XX年の革命家になるには」
(LINKS)
(PROFILE)
山田由梨 / Yuri Yamada
1992年東京生まれ。作家・演出家・俳優。立教大学在学中に「贅沢貧乏」を旗揚げ。俳優として映画・ドラマ・CMへ出演するほか、小説執筆、ドラマ脚本・監督も手がける。『フィクション・シティー』(17年)、『ミクスチュア』(19年)で岸田國士戯曲賞ノミネート。セゾン文化財団セゾン・フェローI。Abema TV「17.3 about a sex」「30までにとうるさくて」脚本。NHK「作りたい女と食べたい女」脚本。WOWOW「にんげんこわい」では脚本・監督として参加。
(LINKS)
(TAG)
(SHARE)
(02)
関連するイベントと記事
Related Events And Article

関連する
イベントと記事

(Contact)
SHUTLへのお問い合わせ
Launching Authentic Futures SHUTL


SHUTLは現代の表現者が、伝統と出会い直し、時間を超えたコラボレーションを行うことで新たな表現方法を模索する創造活動の実験場です。スペース利用から、メディアへの掲載、コラボレーションまで、どうぞお気軽にお問い合わせください。



